●ABCモデル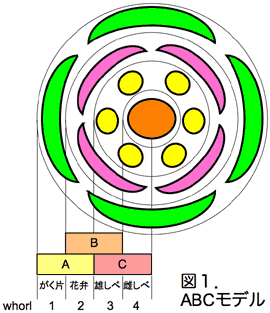 1990年に、花器官形成の単純かつ明快な分子遺伝学的モデル、
1990年に、花器官形成の単純かつ明快な分子遺伝学的モデル、ABCモデルがE. M. Meyerowitzのグループにより提唱された。 このモデルはシロイヌナズナの研究より考えられたが、 他の植物にもABCモデルを当てはめることができる。 図1に示すように、花器官は4つの同心円状の領域(whorl1-4) に、それぞれがく片、花弁、雄しべ、雌しべが並んでいる。 花器官を形成するための3つのクラスの遺伝子(クラスA, B, C)が、 隣り合った2つのwhorlで発現し、その組み合わせにより どの花器官が形成されるかが決定する。 クラスAの遺伝子のみが働くと「がく片」 クラスAとクラスBの遺伝子が働くと「花弁」 クラスBとクラスCの遺伝子が働くと「雄しべ」 クラスCの遺伝子のみが働くと「雌しべ」が形成される。 クラスBの遺伝子の機能が欠失した場合、 whorl2ではクラスA、whorl3ではクラスCの遺伝子のみしか働かないため、 それぞれがく片、雌しべが形成される(図2)。 また、クラスAとクラスCの遺伝子はお互いにその働きを抑制しており、 クラスAの遺伝子の機能が欠失するとクラスCの遺伝子が whorl1および2の領域でも働き、結果として 雌しべ、雄しべ、雄しべ、雌しべという花ができる(図3)。 逆にクラスCが欠失するとがく片、花弁、花弁、がく片となり(図4)、 さらにwhorl4で新たな花が繰り返し形成されるため、八重咲きの花になる。 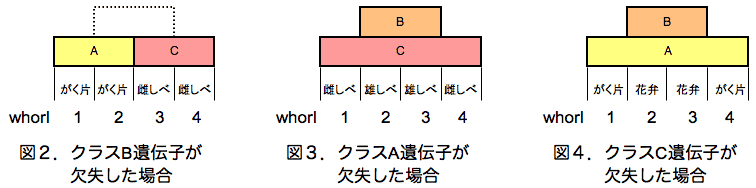
|